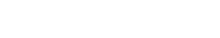令和3年12月4日 射手座新月

12月に入ると、真冬並みの寒さになり、若干寒さも和らぐ時もあります。しかし、年を重ねる度に芯に身にしみて寒さを感じるのはわたしだけでしょうか。
桜特集 滝匂(タキニオイ)
滝匂(タキニオイ)は花は白く、幹は直立し、枝の並びは横に広がる落葉高木で高さは8~10m,直径25~30cmとなります。香りが強いのが特徴で、典型的なオオシマザクラです。また、花弁数は5~7枚で先の方は淡紅色になっており、花弁は長さが1,6~1,8cm,幅は1,0~1,2cmで先端は2裂します。開花期は4月下旬です。
愛パークにも入り口から右側の斜面に妹背(イモセ)が3本ある並びに滝匂が斜面に沿って10本程あります。開花時期になると匂いが辺りに立ち込めて、白色の花弁を付けた滝匂(タキニオイ)が堂々と立ってすぐ分かります。
『桜の樹皮は(桜皮《おうひ》)は漢方薬』
桜の桜皮(おうひ)は日本の民間薬として開発されたもので江戸時代の民間療法の書物に多く収蔵されています。
薬用にする桜皮(おうひ)は、山地に自生するヤマザクラが主です。桜皮(おうひ)には、鎮咳作用があり、咳止めとして服用されてきました。特に6~8月ごろ桜皮(おうひ)をはいで天日で乾燥させ、生薬としました。せきにはこの乾燥樹皮を煎じ服用すると効果があるようです。しゃっくりには、桜の樹皮を黒焼きにし、粉にして白湯で用いたり、二日酔いには桜の皮を煎じて飲んだり、おできには樹皮を煎じた煎液で患部を洗うなどして用いていたようです。また、幕末の花岡星州が創案した十味敗毒湯にも樹皮が用いられて来ました。他にも急性湿疹、水虫、化膿性疾患や皮膚疾患にも使用されたようです。昔の人々は薬は植物から作って病気を治していたのですね。先人の人々はいろんな工夫をしていたことが伺えます。
【桜さくらサクラ100の素顔】より引用 良子(*^o^*)
次回は12月19日双子座満月です。お楽しみに(*⌒▽⌒*)